 にわじい
にわじい介護施設の種類が多くて、どれにすればいいのじゃ?



自分の生活スタイルに合った施設がオススメだよ!
介護施設を探し始めたとき、「種類が多すぎて、どれを選べばいいの?」🤔と感じたことはありませんか?
私もまったく同じ状況でした。
特養・有料ホーム・サ高住…、それぞれの特徴を調べても違いがよく分からず、頭の中が整理できない。😰
そんなとき、担当のソーシャルワーカー👩⚕️からの一言が、私の考えを大きく変えました。
「施設の種類より、“お父様がどんな暮らしを望んでいるか”を考えてみましょう。」
この記事では、私が実際に迷った体験をもとに、ソーシャルワーカーの助言で気づいた“正しい選び方”のポイントを、わかりやすく解説します。
同じように迷っている方の参考になれば幸いです。
✅結論:施設は“種類”で迷うより、本人が望む「生活スタイル」で選ぶと整理できる
✅主要な介護施設(特養・有料・サ高住・老健・GH)の特徴と「向いている人」
✅迷いやすい3点(入所までの期間/相談の仕方/他候補を外した理由)を、実体験で具体化
✅ソーシャルワーカーができること・無料で相談できる範囲・連携先(ケアマネ等)
介護施設の種類が多くて迷う…結論:「本人の生活スタイル」で選ぶのが正解
介護施設を選ぶとき、その種類の多さから、ほとんどの人が迷っているのではないでしょうか。
結論から言うと、「本人が希望する生活スタイルを実現できる施設」を選ぶことが最適です。
もちろん、入所に関して諸々の条件はありますが、本人の希望を軸にすることで選び方が絞られていきます。
詳しく解説します。
介護施設を選ぶとき、多くの人が最初につまずくのが「種類の多さ」です。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護付き有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 介護老人保健施設(老健)
名前は似ていても、目的もサービス内容もそれぞれ違います。
私も最初は、「どれが正解なんだろう?」と、パンフレットを並べて比べてみました。📕📖📘
けれど、費用や設備を眺めても、答えは出ません。🤔
むしろ、情報が増えるほど混乱していくばかりでした。😭
そんな中でソーシャルワーカー👩⚕️に言われた言葉が、いまでも印象に残っています。
圧迫骨折で車椅子生活を送っている父の希望は
🚶♂️「以前のように歩けるようになりたい」
🍚「食事の心配をしないで、穏やかに暮らしたい」
父の希望を考えると、自然と候補が絞られていきました。
“種類”という制度上の分類ではなく、“本人の生活スタイル”に合うかどうか。
この視点を持つだけで、選び方が驚くほどシンプルになります。
まだ介護保険の申請をしておらず、「要介護認定ってどうやるの?」という方は、こちらの記事を先に読んでおくと、手続きの全体像がつかめます。
⏩「介護保険の申請が不安な人へ|親の要介護認定までの流れと体験談」
介護施設の種類をわかりやすく整理|特徴と向いている人を把握しよう
介護施設といっても、実際には目的やサービスの内容が大きく異なります。
ここでは「どんな人に向いているか」を軸に、代表的な施設の特徴をわかりやすく整理してみます。
✅特徴
- 介護保険が適用され、入居費用が比較的易い公的施設。
✅向いている人
- 要介護3以上で、日常生活に介助が必要な方。
- 長期的に安心して生活したい方。
✅注意点
- 人気が高く、入所待機が発生しやすい。
- 医療ケアよりも介護ケアに重点を置いている。
✅特徴
- 民間運営で、介護スタッフが24時間常駐。介護度が高くても入居できるケースが多い。
✅向いている人
- 医療・介護の両面でサポートが必要な方。
- 家族が頻繁に面会できない方。
✅注意点
- サポート体制が充実している分、費用が高め。
- 選択肢が多く、選ぶのに時間がかかる。
✅特徴
- 高齢者向けのバリアフリー賃貸住宅で、見守りや生活支援が中心。
✅向いている人
- 自立または軽度の介護が必要な方。
- 「自由な暮らし」を維持したい方。
✅注意点
- 介護サービスは外部契約になるため、介護度が上がったときは追加費用が発生する。
- 要介護度が高くなり対応が困難になった場合、退去の可能性がある。
✅特徴
- 医師やリハビリスタッフが常駐し、「在宅復帰」を目的とした公的施設。
✅向いている人
- 退院後のリハビリや一時的な入所を希望する方。
- 自宅での生活に戻る準備をしたい方。
✅注意点
- あくまで「一時的な利用」を前提としており、長期入所には向かない。
- 生活支援サービスやレクが少ない。
✅特徴
- 少人数で共同生活を送る家庭的な雰囲気の施設。認知症ケアに特化。
✅向いている人
- 軽〜中度の認知症がある方。
- アットホームな環境で暮らしたい方。
✅注意点
- 地域密着型サービスのため、原則として住民票が同じ市区町村にあることが条件。
- 定員が少ないため入居待ちが生じる場合がある。
💬 制度で比べるより“暮らし方”で考えよう
介護施設の違いは制度や仕組みの差から生じる部分が大きいです。
実際に暮らす本人や家族にとって大切なのは、「本人が望む生活を送れる施設はどこか?」です。
この視点を持つことで、数ある選択肢の中から自然に“自分たちに合う施設”が見えてきます。
種類を理解したら、次は「選ぶ軸(費用・場所)」で現実的に絞り込みましょう。
⏩介護施設の選び方で失敗しない!『費用』と『場所』がいちばん大切な理由
迷った3つのポイント|“種類”よりも“父の暮らし方”を考える転換点
父が自宅で転倒して圧迫骨折。寝たきりの生活が突然始まりました。
治療のため入院したものの歩行が困難になり、車椅子での生活が中心に。
医師からは「リハビリを続ければ歩ける可能性はある」と言われましたが、自宅でのリハビリ環境を整えるのは現実的に難しいと感じました。
そしてもう一つ、私たちには大きな制約がありました。
病院の入院期間が“3ヶ月”と決まっていたのです。
そのため、退院までに入所先を見つけなければならないというプレッシャーがありました。
自宅復帰は難しい。では、どんな施設が父に合うのか──。
ここから本格的な施設探しが始まりました。
🔹 ① 「どの施設がいいのか」より「どこに入れるのか」
まず最初に考えたのは、入所までの期間です。
特別養護老人ホーム(特養)は費用が安く魅力的でしたが、待機期間が長く、3ヶ月以内の入所は難しいと判断しました。
入居できる施設が見つかるまで転院を繰り返す方法もありますが、3ヶ月毎の転院は父に過大な負担を掛けるため現実的ではありません。
「入れる施設」を探すことが優先せざるを得ない状況でしたが、それでも「父の希望する暮らし方」を諦めたくありませんでした。
「待機が長い」と分かったときは、空き待ち期間のつなぎ方も同時に考えると安心です。
⏩希望施設が満床だったときの選択肢(同系列で仮入所→本入所)
🔹 ② ソーシャルワーカーに相談して見えた方向性
悩んだ末、担当のソーシャルワーカーに現状をすべて伝えました。
- 圧迫骨折による車椅子生活
- リハビリの必要性
- 自宅復帰の困難さ
- 限られた期間での施設探し
ソーシャルワーカーさんは一通り聞いたあと、こう助言してくれました。
👩⚕️「お父様のように医療とリハビリの両方が必要な場合は、介護付き有料老人ホームが一番現実的ですよ。」
実は、私自身も同じように考えていたので、この助言を聞いてすっと気持ちが整理されたのを覚えています。
介護施設を選ぶのに「制度上の分類」で迷っていたことが、”父の生活に必要な支援で選ぶ”という考え方に変わった瞬間でした。
🔹 ③ 他の選択肢をどう判断したか
ソーシャルワーカーさんからの助言を受け、検討を重ねた結果、介護付き有料老人ホームに決めました。
医療連携があり、介護サービスが充実している点も安心材料のひとつ。
他の候補も検討しましたが、以下の理由で除外しました。
| 施設名 | 検討結果・理由 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 待機期間が長く、3ヶ月以内の入所が難しい |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 介護サービスが外部契約のため、対応面に不安 |
| 介護老人保健施設(老健) | 自宅復帰が前提のため、父の状況には合わない |
| グループホーム | 認知症ケアが中心で、介護体制が十分ではない |
誤解してほしくないのですが、「介護付き有料老人ホームが最も良い」と言っているわけではありません。
🚩待機期間に余裕があれば特別養護老人ホームを検討したでしょう。
🚩車椅子でなければサービス付き高齢者向け住宅も検討したでしょう。
介護の度合いや健康状態、本人の希望する生活スタイルから総合的に判断することが大切です。
まずは介護サービスを使う土台(要介護認定)を押さえると、施設選びが一気に進みます。
⏩介護保険の申請が不安な人へ|親の要介護認定までの流れと体験談
💬 迷いを経て見えた「本当の選び方」
当時は「どの施設に入れるか」を最優先に探していましたが、結果的に一番大切だったのは、「父が安心して過ごせる生活の形」でした。
ソーシャルワーカーの助言がなければ、今も「費用」「待機」「立地」といった条件だけで迷い続けていたかもしれません。
ソーシャルワーカーについて簡単に解説します
父の施設選びで大きな助けになったのが、ソーシャルワーカーさんでした。
そもそも「ソーシャルワーカー」とはどんな人なのか、どんなことをしてくれるのか──
ここで少し整理しておきます。
🔹 ソーシャルワーカーとは?
正式名称は「社会福祉士」または、病院などで働く場合は「医療ソーシャルワーカー(MSW)」と呼ばれます。
福祉や医療の制度のもとで、本人や家族の希望を聞き取り、必要な支援につなげる暮らしの相談窓口のような存在です。
制度の案内や手続きの支援だけでなく、退院後の生活設計、介護サービスや施設の相談、医療機関・行政・地域の支援機関との連携調整など、幅広い役割を担っています。
🔹 ソーシャルワーカーがしてくれる主なサポート
- 本人と家族の状況を聞き取り、困りごとや希望を整理する
- 使える制度(介護保険・医療費助成・障害福祉・生活支援など)を案内し、手続きの流れをサポート
- 退院後の生活や療養の見通しを立て、在宅サービスや施設の選択肢を一緒に検討する
- 病院(医師・看護師・リハビリ職)や地域(ケアマネ・包括支援センター・行政・事業者)との連携調整
- 状況の変化に応じて、支援内容を見直し、必要な窓口へつなぎ直す
つまりソーシャルワーカーは、医療・福祉の制度と、本人・家族の生活をつなぐ橋渡し役です。
制度や支援先が複雑な中でも、現実的な選択肢を整理してくれる頼もしい存在です。
相談先が多くて迷うときは、「最初の窓口」を決めるだけでラクになります。
⏩親の介護、まずどこに相談すればいい?|区役所・地域包括・病院…
🔹 ソーシャルワーカーへの相談は無料でできる
病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)への相談は、原則として無料です。
入院中の困りごとや退院後の生活、介護サービスや施設のことなど、幅広く相談できます。
また、地域の相談先としては「地域包括支援センター」や市区町村の福祉課でも相談窓口があり、必要に応じて適切な支援機関につないでもらえます。
さらに、介護保険の申請や要介護認定がまだの場合でも、ソーシャルワーカーに相談すると、申請の流れを整理しながら、担当のケアマネ(介護支援専門員)へスムーズにつなげてもらえることがあります。
💬 ソーシャルワーカーに相談をした感想
介護施設を探し始めると様々な問題に直面しました。
- 制度が分からない
- 用語が分からない
- 何をどうすればいいのか分からない
😭とにかく分からないことのオンパレードでした・・・
そんな中、頼りになったのが👩⚕️ソーシャルワーカーさん。
こちらの疑問に対して適切な回答をしてくれるし、欲しいと思っている情報を先回りして手配してくれたりと、とても助かりました。
家族だけで判断しようとすると、どうしても視野が狭くなりがちです。
ソーシャルワーカーに相談することで、医療・介護・生活支援を含めた選択肢が見えてきます。
介護施設を探すときは、最初にソーシャルワーカーと一緒に状況を整理してから始めるのがオススメです。
次の章では、そのソーシャルワーカーの助言をどのように活かして「正しい選び方」を見つけたのかを、具体的に紹介します。
“選び方”に正解はない。大切なのは“納得できる選び方”
介護施設を選ぶとき、多くの人が「正解を探そう」とします。
だれでも失敗は避けたいので当然ですよね。
けれど、実際に体験して分かったのは”介護に正解はない”ということ。
大切なのは、「自分たち家族が納得できる選び方」をすることです。
施設の種類や費用、立地や設備など、どれも大事な要素ですが、最後に決め手になるのは、”本人がどんな暮らしを望むか”いう一点でした。
私の場合、父の入所先を決めるまでに何度も迷いました。🤔
でも、ソーシャルワーカーの助言や家族の話し合いを通じて、「父が穏やかに過ごせる場所」を軸に考えたことで、最終的に心から納得できました。😊
“施設を選んだ”というより、“父の暮らし方を選んだ”という感覚に近い気がします。
介護施設探しは、情報よりも気持ちの整理が難しいものです。
迷うことは悪いことではなく、それだけ「大切な人の生活を真剣に考えている」証拠です。
だからこそ、焦らず、抱え込まず、ソーシャルワーカーや専門職に相談しながら、納得できる選択をしていきましょう。
あなたやご家族が安心できる居場所が、きっと見つかります。
施設が決まりそうになると、次に不安なのが「入居後の生活のリアル」です。
⏩老人ホームの1日をやさしく紹介|入居後の暮らしに不安がある方へ
次に読むなら
「最初の一歩」を迷わないための“相談先の地図”が手に入り、次に何を聞けばいいかまで整理できます。
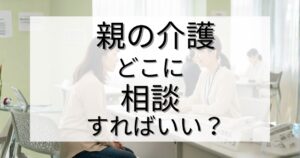
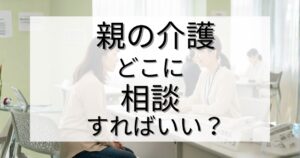
施設の種類で迷う前に、予算と通える距離で候補を絞る方法がわかり、比較が一気にラクになります。
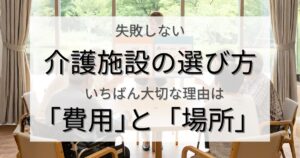
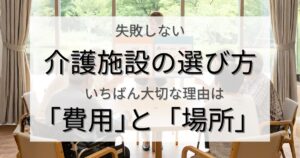
パンフやHPでは見えない“現場の空気”をチェックする具体的な見学ポイント(7項目)がわかり、見学後の判断がブレにくくなります。
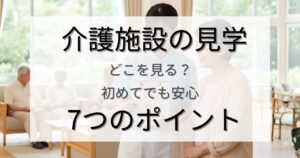
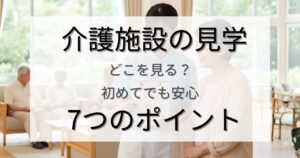
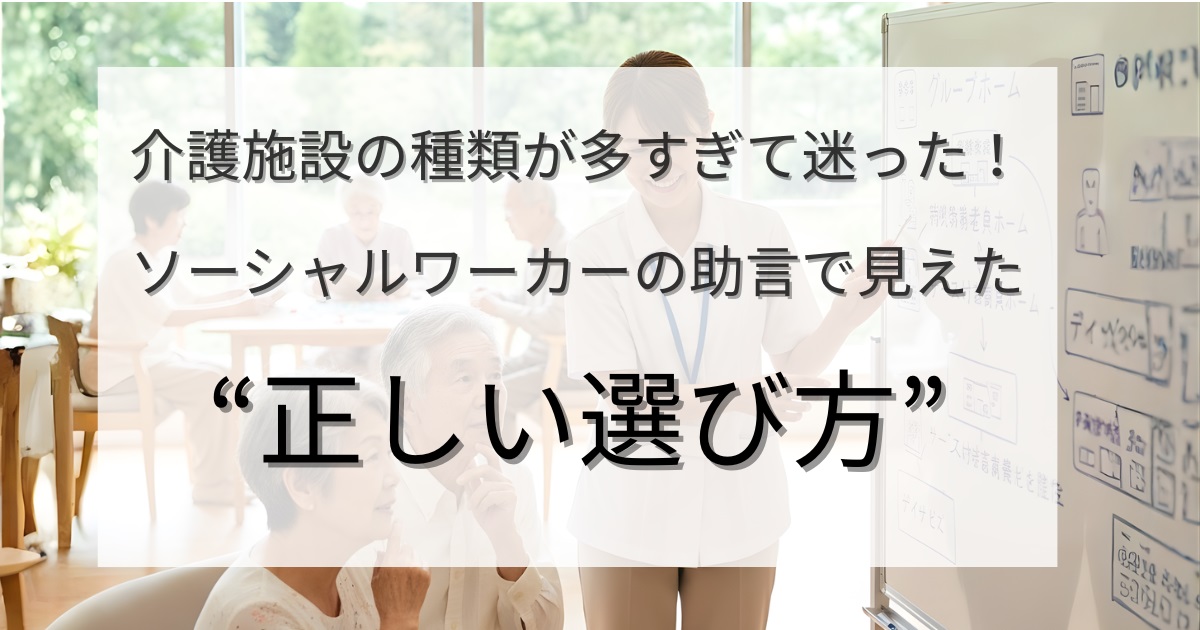
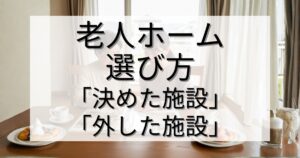
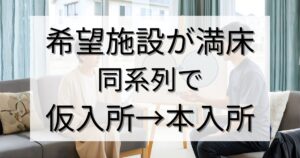
コメント